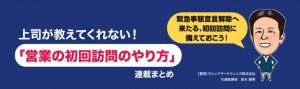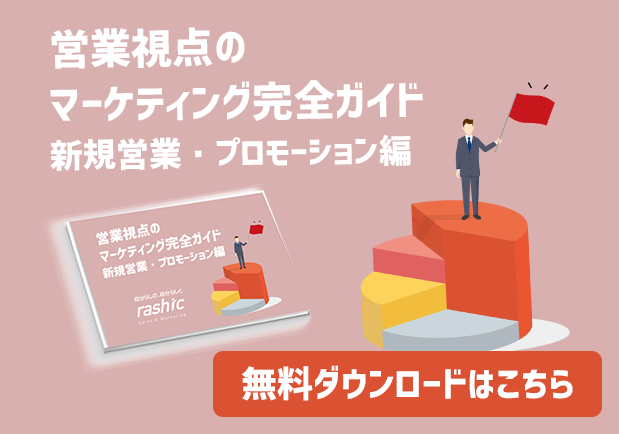営業・マーケティングの実行編、ますはコンテンツづくりの重要ポイント「コンテンツ設計」です。ペルソナ、狙うキーワードだけでなく、ブログ、ダウンロード資料、コンテンツマッピングと抑えるポイントや書き方があります。コンテンツ設計のやり方について、整理しました。
目次
コンテンツづくりの重要ポイント「コンテンツ設計」とは?
もう一度、ここまで第二章までのブログを振り返ってみる。インバウンドマーケティングは営業の新規開拓効率が上がるので、マーケティング部は営業が新規開拓に費やす時間を削減することに寄与できる。そして営業部は人から入る新規開拓に集中できる。そのためには顧客の自然検索から自社の製品・サービスの見込みにつなげるキーワードを上位表示させる必要がある。検索エンジンのアルゴリズムは「読み手のためになっている有益で信頼できる記事か」というポイントも理解できた。狙うペルソナ、狙うキーワードも決めた。ではここからはインバウンドマーケティングをどのように実践していけばいいのだろうか? 第2章:企画編で記載した狙うペルソナ、狙うキーワードから、「誰に」「何を」伝えるかをもう一度記載したい。
コンテンツ設計で整理しよう!「ペルソナと狙うキーワード」
■狙うペルソナ 「誰に」 経理の人
経理部主任と経理部長の視点で課題解決を考えている、経理の人 (例)
■狙うキーワード 「何を」伝えるのか →「経費精算 〇〇」 (例)
〇〇とは「ルール」 「手法」のような認知や気づきの段階のような潜在キーワード
「システム」や「ソフト」のような解決手段を求める顕在キーワード
このペルソナとキーワードに対しコンテンツを提供していくためのコンテンツ設計をしていく。まずに何をしていくかというと「どのキーワードに対し、どんなコンテンツを提供していくか」を設計していくことが第一段階である。この時のペルソナのマーケティングステージは「見知らぬ人」か「サブスクライバー直前」の状態である。つまり「認知・気づき」の更に前の段階と言える。前述した経費精算クラウドのペルソナ例で言えば、経理部主任が経費精算に時間がかかっていて、やり方がまずいのかな・・と課題はまだボヤッとしている。
「他の会社の経理部の人はどうしているのだろう?」と検索エンジンで軽く検索してみた状態としよう。経理部主任が「経費精算 やり方」と入力して、その自然検索上位に自社の製品・サービスのページがいれば、クリックしてくれる確立が高いわけだ。ここまでは誰でもイメージできると思う。その時のページは自社の製品ページの特長や機能のページであればサイコーだ。私もそう思うし、そうなってほしい。だがこの段階では特長や機能のページが検索上位にいることは難しい。その理由は顧客の課題がまだ顕在化していないからだ。課題が顕在化していないと人は解決策へ向かっては動かない。「他の人はどうしているのだろう?」「何か参考になるものはないかな」という潜在的な状態なので、学べるような参考情報を欲しがる。この情報を提供するベストな手段がブログなのだ。
営業・マーケティングのコンテンツ設計の中心は、ブログ
例えばそのブログは「経費精算のやり方を5つの事例とステップで徹底解説」だとすると、経理部主任の今の気持ちに近いのではないだろうか。このように課題やニーズが顕在化していない初期段階の人に対する気持ちに対し、キーワードを決め、ブログで応えていくための設計をしていく。初期段階のサブスクライバーに対して、製品ページの特長や機能の情報を提供することはマッチしていない。製品ページには課題やニーズが顕在化した顧客に対する情報を掲載するべきだ。つまり製品ページは自社の製品・サービスに関心や比較検討のステージになった人に提供するページなのだ。
それに対しブログは具体的な製品・サービスの情報だけを発信するものではないので、このような潜在的な顧客に対する情報提供や学びのための資料にしやすい。だからインバウンドマーケティングに力を入れている企業は、初期段階の潜在層にリーチするためにブログをたくさん書いているのだ。狙うキーワードに対しどんなブログを書いていくのか決めて、今後半年から1年間のブログスケジュールを計画する。そのブログにインデックスが貼られれば、アクセスされるようになりセッション数が増え、そうなると自然検索で上位にいき、更にセッションを増やす、を繰り返していく。そうやって検索上位を目指していくのである。
製品サイトの機能や特長のページ比べ、ブログページはどんどん更新をしていけるので、検索エンジンのアルゴリズムの「更新性を高める」にも対応しやすい。読み手に対して有益な情報をたくさん提供していれば「コンテンツが充実」というアルゴリズム要件も満たしている。このように狙うキーワードに対して良いブログを定期的にたくさん提供していくと、ブログ投入→自然検索で上位にいく→セッション数が増える→リードとMQLが増えるというサイクルになるのだ。これはインバウンドマーケティングのコンテンツ設計の根幹である。
ブログは個人情報を入力しなくても読めるようにする。ブログを読むために定期購読を申し込んでくれてもメールアドレスが取得できるぐらいで、これはまだコンバージョンともリードとも呼ばない。サブスクライバーだ。多くの顧客はブログを読んで終わりだ。顧客の購買プロセスは「こんな製品・サービスをやっている会社があるのか」とやっと認知して気づいてくれたぐらいだろう。この認知・気づきから「学び・興味・関心に」いくためには次に何を設計していけばいいだろう?顧客には再度違うブログを読んでもらったり、資料をダウンロードしてもらったり、できれば自社の製品ページの特長や機能を見てほしい。つまり顧客の購買プロセスとマーケティングステージに対して、細かく提供していくコンテンツを決めなければならない。次に行う設計作業がコンテンツマッピングだ。
-1024x576.jpg)
コンテンツ設計のために、コンテンツマッピングをする
プロセス設計図内の、顧客の購買プロセスとマーケティングステージに対して、提供していくコンテンツを細かく決めなければならない。この作業をコンテンツマッピングという。図2のコンテンツマッピングに関する資料を見てほしい。顧客の購買プロセスから顧客の状態に細分化して現在どのような問題や課題があるのか、つまり提供するべきコンテンツはどういうものがよいのかを決めていくのだ。そしてコンバージョン時に入力する項目をフォーム設計していく。これらのやり方はこの後のブログの、コンテンツ作成→コンテンツ提供で記載していきたい。
前述したようにサブスクライバーの顧客には狙うキーワードのブログをひたすら設計し、ブログを徹底的に供給していく。顧客が「ためになることを知りたい」、「役に立つものが読みたい」という想いを重視してブログを作成していこう。また定期購読を希望する顧客にはたくさんのヒアリング項目を設けない。メールアドレス入力だけで購読できるようにする。まずは今後もブログを定期提供できる関係づくりができればそれでいい。コンバージョンするフォーム設計はその先だ。
ブログとセットの関係「ダウンロード資料」
リードの顧客へのコンテンツフォーマットはダウンロード資料だ。ここでガッチリとコンバージョンをしてもらうフォーム設計をして、リードになる。コンテンツはキーワードに関する資料になるが、資料の内容は2種類に分けられる。
➀学びの資料・・・手法や基本を学びたい
②製品・サービス資料・・具体的な課題解決方法を教えてほしい
例えば「経費精算 ルール」のキーワードで検索した顧客が「経費精算で経理部が困っている精算ルール違反6選」のブログを読んだとする。これは認知・気づきの段階だ。「そうそう!月末にそんなルール違反で困っているよ」と顧客が共感したとする。次に顧客を学びの状態に持っていくためのダウンロード資料は「経費精算の社内ルールブックテンプレート集」だとする。「実際にもう少し学びたいな、ルール作りの準備になればいいな」という気持ちになっていてコンバージョンするかもしれない。具体的にもっと学び、実践をしていきたい!と思ってくるのなら「経理部が実行している組織作り:経費精算編」というダウンロード資料もいいかもしれない。
このように手法や基本を学び、具体的な課題解決方法を教える資料を提供していくと、顧客はコンバージョンしてくれやすい。そうしてリードにしていくのだ。製品・サービス紹介資料や基本ガイドも用意しておくが、順番は➀学びの資料、その次に②製品・サービス資料だ。いきなり製品・サービスに関する資料を提供している製品サイトが多いと感じている。リードにしてナーチャリング実践で育成していきながら、興味関心の状態にして製品・サービス資料を提供するのだ。
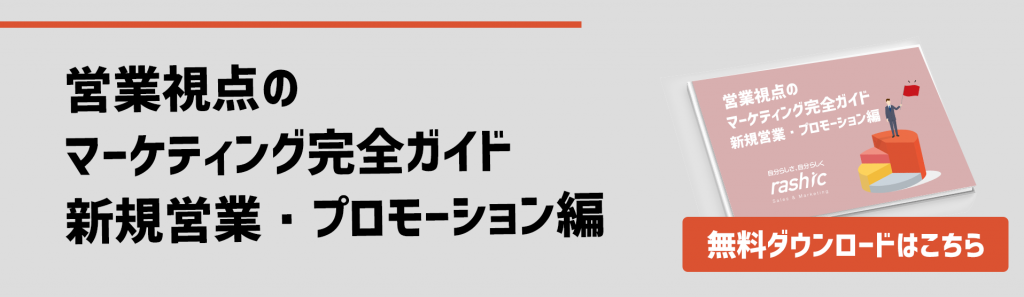
営業・マーケティングのコンテンツ設計のやり方とは? まとめ
コンテンツづくりで最初に行うコンテンツ設計、「なぜまずブログなのか?」というブログの在り方について理解いただけたと思う。そしてその次に購買プロセスとマーケティングステージに合わせ、ダウンロード資料を考えていくコンテンツマッピングの作業をしていくことも理解いただけたと思う。プロセス設計図から新規開拓に対して、インバウンドマーケティングの心臓部・コンテンツづくりのコンテンツ設計がこれで完了した。次はいよいよコンテンツ作成に入っていこう。
- マーケティングは、CTAでダウンロード資料を伝える
- 営業・マーケティングは「資料ダウンロード」でリードを取る
- 営業・マーケティングチームのブログ作成の方法とは?おすすめのやり方をご紹介 その2
- 営業・マーケティングチームのブログの書き方とは?初心者が学べるコツをご紹介 その1
- 営業・マーケティングのコンテンツ設計のやり方とは?
- 【2022年最新】BtoBマーケティング事例 3つの面白い傾向を発見
- 営業ブログ ノウハウを新規開拓営業に使う、全く新しい方法
- プッシュ営業はやりすぎ注意!プル営業の質の良さを取り入れよう
- ブログを企業の人材育成へ使う方法 営業・マーケだけじゃない!
- ブログの始め方 営業・マーケティング新規活動の常識へ
- オウンドメディアとインバウンドマーケティングの違いとは?
- Google Search Console(サーチコンソール)の使い方とは?インバウンドマーケティングで使いこなすための見方
- Google Search Console(サーチコンソール)とグーグルアナリティクスの違いをインバウンドマーケティング視点から解説【初心者向け】
- 最強の新規開拓手法 インバウンドマーケティングに企業対応するためのポイントとは?
- どうすればインバウンドマーケティングと呼べるのか? 企業で使うための意味と手法を解説
- ブログを書けばインバウンドマーケティングと思っているあなたに~その事例と、まずやるべきことを解説~
- 伝わる製品キャッチに変えて新規開拓営業をやってみよう!
- 新規営業のトレンドとは? 2021
- マーケティングは、CTAでダウンロード資料を伝える
- 営業・マーケティングは「資料ダウンロード」でリードを取る
- 営業・マーケティングチームのブログ作成の方法とは?おすすめのやり方をご紹介 その2
- 営業・マーケティングチームのブログの書き方とは?初心者が学べるコツをご紹介 その1
- 営業・マーケティングのコンテンツ設計のやり方とは?
- インバウンドマーケティングのために製品ページのリニューアルは必要か?
- 検索エンジンのアルゴリズムを理解して、インバウンドマーケティングを実行してみよう