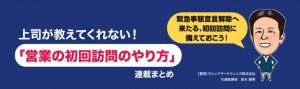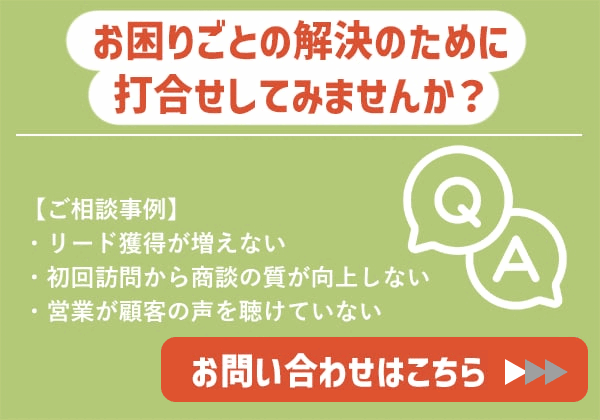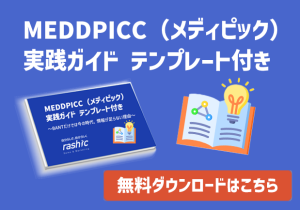営業資料の作り方には様々な方法があります。誰でも製品の価値を顧客に素早く伝えられるようにしたいと思うはずです。そして、営業資料はパワーポイントで作成し、見やすくてわかりやすいものにしていきます。本記事では、視覚的で顧客に伝わりやすい営業資料の作り方を解説していきます。
営業資料作成のコツは「構成が命」であり、ヒントは「大から小」「興味→共感→解決」「3つの特長」にありました。みなさんに具体的なイメージを持ってもらうために、IT業界で製品を持っている例でご説明していきます。もちろん、他の業種の商品や製品・サービスでも当てはまる内容ですので、ぜひ参考にしてください。
目次
営業資料とは製品を一緒に紹介してくれる右腕
営業資料とは営業が顧客に製品を紹介する時に使用するものです。言葉だけで話しても製品の良さはなかなか伝わりませんし、チラシレベルの資料では製品が安っぽく見えてしまいます。
視覚的で見やすい資料と共に営業が説明をすると、顧客に製品の価値が伝わりやすくなります。営業資料はまさに営業の右腕であり、営業と一緒に価値を届けてくれる相棒と言えます。
どんなに話し方が上手い営業でも言葉だけの製品紹介では、良さは伝わりにくいものです。営業資料と共に話すということは、共有できるカタチに整えて顧客に伝えようと話し始めています。「営業資料と共に話す」という作業を「営業が説明すること」と私は定義しています。
つまり、「話す」と「説明する」は意味が違うのです。営業資料と共に話して、顧客に製品の価値を伝えていきましょう!詳しくは下記記事をご覧ください。
資料作成時の注意点 このポイントは抑えておこう
営業資料を作成するにあたり、ひとつだけ注意点があります。このポイントだけでは営業チームで協議してみてください。それは「外に出してもよい内容である営業資料」ということです。
リモート商談が増えて、顧客から「あとで先ほどの資料をメールで送ってください」というシーンが増えています。後日、営業資料をPDFでメール送付するわけですが、ファイルで送ると誰でもどこにでも転送ができます。
社内の関係する部署に「良い製品がるので資料を見てください」と転送し、共有してもらえるケースはメール送付の良さが出ます。
しかし、競合他社に転送されてしまったり、新製品開発のアイデアに使われてしまったりするケースは少なくありません。つまり、「外に出してもよい内容である営業資料」は、製品の核心になる部分を外し、競合他社に入手されても良いレベルの内容にしておきましょう。
ラーメン屋に例えるとラーメンの作り方は公開しても、スープの作り方は教えてないというイメージですね。
営業資料の基本構成は、コンセプトや特長、事例や機能に関するものを営業資料のベースとするべきです。製品の画面一覧や細かくテクノロジーを説明している資料、価格や費用に関する資料は「営業資料」から外し、「詳細資料」として2段階の製品紹介資料にしておくと使いやすいと思います。
製品の基本的な内容が「営業資料」、核心に触れているものが「詳細資料」というイメージですね。
価格や費用を製品サイトに公開している製品は営業資料に盛り込むようにしましょう。営業資料を作成するにあたり、「外に出してもよい内容である営業資料」にするのは重要なポイントですので、営業チームでよく話し合って作成していきましょう。
7つのやり方に売上向上のヒントが隠されている
営業・マーケティング 7つのやり方 サービス基本ガイド
資料はパワーポイントで作成してみよう
営業資料はパワーポイントで作成するのが最近ではほとんどのケースです。Googleスライドも増えていますし、パワーポイントでもGoogleスライドのどちらでも良いと思います。なぜなら、ワードやエクセルに比べ、視覚的で見やすい資料が作成できるからです。
パワーポイントで営業資料を作成できるようになるまでは、機能や操作を理解することだけでなく、一定の経験値が必要です。様々な製品・サービスの紹介資料や個別の提案資料を数多く作ってみて、パワーポイントで資料を作成するコツを習得していきましょう。とにかく、実践あるのみ!と言えます。
私がオススメするパワーポイントで資料が早く作れるようになるコツは、初回訪問で顧客の問題点を聴いた後に、次のようにまとめてみるやり方です。
- 現状業務の問題点を箇条書きにする
- 製品の●●機能や〇〇運用で解決 解決策を提示する
- ご提案のポイント 3つに整理する
パワーポイントに3枚でもいいですし、A3資料1枚でもいいので、顧客の声をまとめてあげましょう。2回目に訪問するネタにもなりますし、顧客も「自分の悩みしっかり聴いていて、問題点を理解してくれている」と感心してもらえるはずです。
最初は時間がかかるかもしれませんが、「時間はかけない意識」を持って作成していきましょう。何度も作成しているとパワーポイントにも慣れ、経験値が上がってきます。大事なマインドは「自分と一緒に説明してくれる相棒を作り、顧客に価値を伝える」という想いです。
もっと複雑で大量な提案書作成を作る時に、必ず役に立ちますので「パワーポイントで資料が早く作れるようになるコツ」をぜひ、やってみてください。
パワーポイントで営業資料を作成するにあたり、デザインをきれいに魅せる方法や効率的に作っていく方法もご説明したいのですが、本記事では割愛いたします。数多くのパワーポイントのテクニック記事が掲載されていますので、検索してみて記事をご覧ください。
資料の見やすい作り方 3つのポイント
それでは、デザインの基本やテンプレート提供ではなく、営業資料の見やすい作り方をご説明していきます。様々な資料の見やすい作り方があるのですが、本記事では「構成は大から小が基本」「興味→共感→解決の流れ」「3つの特長を整理」の3つのポイントを詳しくご紹介していきます。
構成は大から小が基本
見にくくて伝わらない営業資料の代表例は「小から小」に展開していく資料です。前半のページから細かな説明から入り、専門用語が連発されているような資料のことです。言いたいことがぎっしりと詰まっていて「すごく出来る製品でしょ!伝わりますか?」と言わんばかりですが、逆に情報量が多すぎて、アタマに入ってきません。
資料の構成は「大から小へ」が基本です。まずは大きな視点やコンセプト、つまり全体を俯瞰できるような内容から前半はスタートし、徐々に細かな説明に入っていく営業資料を目指しましょう。後述する、‘資料づくりの構成を考える‘で詳しくご説明いたします。
興味 →共感 →解決の流れ
人は興味を持たないと話を聞きません。興味を少し持ったとしても、共感できる部分がなければ、説明に食いついてきません。共感できたら、解決先が知りたくなります。営業資料の前半には必ず、興味→共感→解決の流れを作るようにしましょう。
業務改善がテーマだとするとであれば、例えば、導入事例や導入社数で興味を引き、よくある業務改善で困っていることを共感として示し、解決策を提示していけるような流れにしていくと、わかりやすい営業資料になっていきます。こちらも後述する、‘資料づくりの構成を考える‘で詳しくご説明いたします。
3つの特長を整理 特徴と特長の違い
製品には必ず特長があります。特長とは優れた良い部分のことです。特徴とは区別できる部分のことを指します。つまり、製品の良い部分なので‘特徴’ではなく、‘特長’の単語を使うようにしましょう。
特長が上手く整理されていない製品をよく見ます。特長がなかったり、やたら数の多い特長だったりする製品は、優れた良い部分がわかりづらくなります。人間は「3つのポイントぐらいしか覚えられない」と言われています。
製品の特長を3つに絞り、製品の価値をわかりやすく伝えるページを営業資料に必ず加えましょう。特長にも提示する順番がありますが、本記事では割愛いたします。
このような3つのポイントに気をつけながら、見やすくてわかりやすい営業資料を作っていきましょう。では、もっと具体的な営業資料の作り方をご説明していきます。
-1024x576.png)
資料づくりの構成を考える
営業資料づくりは構成が非常に大切です。構成が命と言っても過言ではありません。なぜなら、顧客が営業資料と営業の説明を聞きながら、構成の順番に沿って製品の理解を深めていくからです。
構成を考えるにあたり、図1をご覧ください。資料の見やすい作り方、3つのポイントでご紹介した「大から小」「興味→共感→解決」「3つの特長」の構成が基本になっています。
営業資料は「外に出してもいいもの」だとすると、製品の内容によりますが15ページから20ページぐらいまでが理想的な量だと思います。それよりも少なすぎると「これぐらいのことしができない製品なの?」と顧客に思われてしまいますし、多すぎると「よくわからない、難しそうな製品」と感じられてしまうかもしれません。
「営業資料」と2部構成と前述した「詳細資料」はもっとページ数が多くなっても良いでしょう。「営業資料」は15ページから20ページぐらい、「詳細資料」は長めという構成で作成するとまとめやすくなります。
資料づくりの主な構成を、一例として具体的にご説明していきますので参考にしてください。
表紙とトビラ
表紙は製品名だけでなく、製品キャッチ=製品がわかりやすくひと言で解説されているものにしましょう。トビラとは資料の間に「会社概要」「導入事例」とタイトルだけ説明されているものです。長い営業資料や提案書にはトビラはあった方が良いですが、20ページぐらいの短い営業資料には不要だと思います。
会社概要 又は 会社紹介
「うちの会社のことは当然、知っていますよね」と会社紹介ページがなかったり、深く説明をしなかったりする営業がいます。一般的には会社概要を知らない顧客がほとんどです。仮に会社名を知っていたとしても、顧客は「付き合うべき会社か?信用できる会社か?」という視点で見ています。
実績があるしっかりした会社であり、様々な面白い取組みをしている会社であることをアピールしたいですね。「取引をしたら、御社のプラスになりますよ」という会社紹介のページを1枚作り、ここから説明をスタートしましょう。
導入事例
導入事例を営業資料の後半に持ってくるケースがありますが、私は前半に持ってきた方が良いと思います。なぜなら、著名な導入企業のロゴを見て「あんな大手企業がこの製品を使っているの?」「同業他社のあの会社も利用している!」という「大から小」で言うと、大のイメージを抱いてくれるからです。
後半に持ってくる導入事例は、企業別に抱える課題から製品を選定し、解決できた!という導入事例説明の資料です。前半に持ってくる導入事例は企業ロゴと簡単な説明を1ページで良いので入れておきましょう。
興味を持つページ
興味を持つページは導入事例でもいいですが、より業務に近いテーマが良いでしょう。「興味を持ってもらえる」という視点で、導入実績数、市場データ、メディアが取り上げた情報、制度や義務化が迫っている件(例:保守サポート終了、インボイス導入、税制対応等)が効果的です。
共感を持つページ
「この業務のこんなことで困っていませんか?」等、困っていることや問題点を記載する内容が良いと思います。業務の問題により、「残業が増えている」「非効率で手間がかかる」というような共感も持ってもらう点を記載しましょう。顧客の声として表記してもよいかもしれません。そして、「その問題点を解決できる方法がありますよ」という展開で次のページに向かうことが大切です。
全体像・コンセプト
製品の全体がイメージできる俯瞰図や製品のコンセプトを入れましょう。興味がわき、共感できて、「なんだか解決できそうな製品だぞ!」と顧客が感じたとしても、大きなイメージで包み込むのが、全体像・コンセプトのページです。
「大から小」へ展開していく、さいごの「大」のページと言えます。IT製品であれば、大きな画面イメージや連携図のような製品イメージがつきやすいものが良いでしょう。ただし、ここで業務フローやフローチャートのような専門的な資料を見せると「難しいの?」と思われるので、簡単な俯瞰図レベルにしておきましょう。
3つの特長
製品を3つの特長に絞ります。一番言いたいことを特長3に持ってきて、その後、機能、プラン、価格、導入の進め方、詳細な導入事例等の「小」のページにつなげていくと、営業資料がわかりやすくなります。
本来はもっと細かな構成や営業資料の作り方を、弊社の「初回訪問資料の作り方研修」でお話しているのですが、構成の作り方はこのような大きな観点で進めてみてください。
視覚的でわかりやすい営業資料になり、営業の説明と共に話せるものになるはずです。顧客に伝えたい!という準備や想いが深く、様々な気遣いや配慮ができている営業資料を目指していきましょう。
まとめ
「営業資料の作り方 構成を大から小にするのが作成のコツ」と題して、ご紹介してまいりました。営業資料とは製品を紹介するものであり、営業の説明と一緒に使う右腕・相棒であることがご理解いただけたと思います。
営業資料はパワーポイントで作成していくのがセオリーですが、機能や操作を覚えるよりも、野球のノックのようにとにかく「資料を作成する」という打席に立つ機会を増やしましょう。そうすれば、パワーポイントを使いこなせるようになり、様々な資料づくりができるようになります。そして、資料づくりが楽しくなり、顧客の元に早く届けたい!と思うようになります。
資料の見やすい作り方の3つのポイントは「大から小」「興味→共感→解決」「3つの特長」です。資料づくりの構成を考えるうえで参考にしてみてください。
「説明する」とは営業がただ話すだけでなく、視覚的な資料と一緒に話していることです。そして、顧客に伝えたい!という準備や想いが強くなり、顧客に製品の価値を届けられます。
営業チームで営業資料の標準化を目指して、営業資料の作成を進めてみてください。