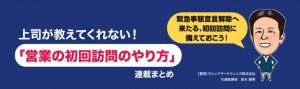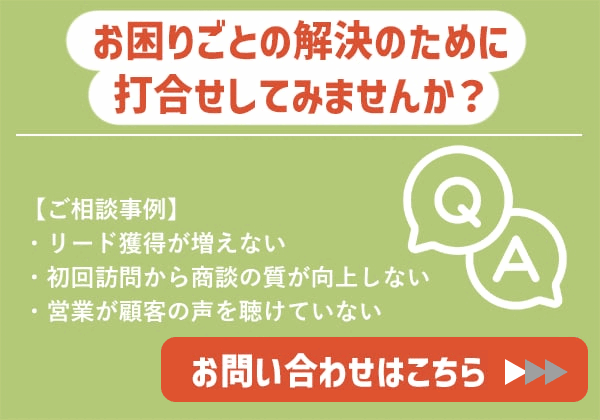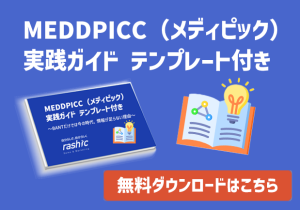GEOという生成AIに対応するためのマーケティング用語が登場してきました。SEOと似ていますし、AIO、LLMOとはどのように違うのでしょうか? 生成AI時代に求められる施策「GEO対策」をいち早く、マーケティング事例を交えながらご紹介していきます。生成AIに選ばれたい企業のみなさま、その方法を詳しく解説いたします。
目次
GEOの意味とは? AI時代に求められるマーケティング施策
GEOとはGenerative Engine Optimizationの略で、生成AIに質問文を入力した際に企業の製品・サービスが選ばれやすいようにサイトやコンテンツを最適化するマーケティング施策です。簡単に言うと「生成AIのエンジンに対する最適化」と言え、目的は「検索や質問をして生成AIに選ばれること」になります。
生成AIに検索や質問して、みなさんの企業の製品・サービスが回答に出れば、検討候補に選ばれる可能性があるかもしれません。もしも検討段階であれば、質が高く良いリードになると言えます。この状態を目指すことがGEOなのです。
しかし、GEOというマーケティング用語に対して、いくつか疑問が浮かびます。これまでよく耳にしたSEO (Search Engine Optimization)に言葉が似ていますし、生成AIを‘エンジン’と呼ぶことや‘検索’することにも違和感があります。いろいろと疑問点がありますので、一問一答形式で整理してみました。
質問 SEO (Search Engine Optimization)とGEO(Generative Engine Optimization)の違いは何ですか?なぜ、名前が似ているのですか?
回答 SEOは検索エンジンの最適化を目指しますが、GEOは生成AIの最適化を目指します。Search =検索、Generative=生成的のそれぞれに対応していく作業や施策と言えます。
質問 検索エンジンと生成AIエンジンの違いは何ですか?
回答 検索エンジンはGoogleのシェアが高く、Googleの検索エンジンが順位を決める検索アルゴリズムを持っています。生成AIも膨大な学習データからテキスト・画像・音声・動画などを生み出すエンジンとも言えますが、生成AIはエンジンというよりも基盤やモデル・機械学習アルゴリズムを組み合わせた頭脳や仕組みのイメージです。いずれにしても、SEOとGEOと語呂や並びが良いので、生成AIもエンジンと呼ばれていると感じます。
質問 生成AIは画像やイラストを作成するための‘生成’がメインなので、検索や質問をするだけならAIと呼べばいいのでは?
回答 複雑なプロンプトを入力して画像やイラストを作成する生成AIに比べ、簡単な認証で質問や検索をする作業はAIと呼んでもいいかもしれません。しかし、過去のAIブームと比べ、現在のAI時代は生成AIに一括りにされているので、生成AIの最適化と呼ばれています。
GEOというマーケティング手法が登場した意味や背景には、このようなポイントがありました。ヨーロッパではGEOという言葉が定着してきていますし、世界的にも統一されてきています。しかし、他にも似たような言葉があるので整理しておきましょう。
SEO、AIO、LLMO、GEOとの違い
SEOとGEOに加え、AIOやLLMOという言葉も存在しています。どれも似たような意味合いなのですが、SEOとGEOという言葉をこれから使っていくためにも、SEO、AIO、LLMO、GEOの意味、目的、範囲、ポイントをまとめてみます。
| SEO | AIO | LLMO | GEO | |
| 略 | Search Engine Optimization | AI Optimization | Large Language Model Optimization | Generative Engine Optimization |
| 対象 | 検索エンジン全般 | AI全般 | LLMO全般 | 生成AI |
| 目的 | 検索エンジンの最適化・検索上位にする | AIの最適化・引用元に入る | LLMOの最適化・引用元に入る | 生成AIの最適化・引用元に入る |
| 今後のポイント | 検索エンジンの上位に表示するためのSEOはこれからも必要である | AIOはGoogle検索結果のトップに表示するAI機能「AI Overview」(AIO)と被っていて混乱するので使いにくい | LLMとは大規模言語モデル(Large Language Model)の意味で、ChatGPTやGeminiを指す。 | LLMも含めて生成AIであり、LLMOが少し長めの言い方で、LLMOはあまり馴染んでいないのでGEOが主流へ |
総括するとAIOもLLMOもGEOとは同じ意味だと言えます。しかし、AIOはGoogleの「AI Overview」と混乱しますし、LLMOは四文字で少し長く、使いにくいと言えます。そして、SEOとGEOの方が語呂もよく、覚えやすいのでGEOに落ち着いたと私は感じています。本記事ではAIOもLLMO もまとめて、GEOと表記し、解説していきます。
生成AIの種類とシェア
GEOはこれから企業に求められる新しいマーケティングですが、その背景には生成AIの企業内での活用が増えていることが挙げられます。そこで、生成AIの種類やシェア、マーケティング視点での利用状況を整理しておきましょう。
| ChatGPT | Copilot | Gemini | perplexity(パープレ) | Claude(クロード) | |
| 2024年シェア | 61% | 16% | 13% | 3% | 2% |
| 種類と特徴 | 企業利用No.1 | Microsoft製品と連携 | GoogleのAI OverviewやAI Modeと連携 | Softbankが搭載してスマホ利用が多い | 開発者のコーディングに強い |
| BtoBマーケティング視点(GA4で見た利用数) | 1位 | 3位 | 4位 | 2位(mobileからが多い) | ほぼGA4では見ないので一般企業向けではない |
※生成AIのシェアは複数のレポートから総合的に判断したおおよその数字になります。
生成AIのシェアや企業向け利用数はこのような結果になっています。ChatGPTやGeminiなどの生成AIで検索したり、質問したりして得られる回答は非常に便利ですので、活用は進んでいるのでしょう。検索したいキーワードを入力して、Google検索結果のトップに表示するAI機能「AI Overview」の回答を見る人も同じです。
これからも企業内の生成AI利用率が上がっていきますし、企業になくてはならない存在と言えます。しかし、ここで起きているマーケティング施策の問題が「ゼロクリック検索の増加」です。
ゼロクリック検索増加の衝撃
ゼロクリック検索とは、生成AIに「●●について教えて」と検索や質問すれば、すぐに回答が得られるため、ウェブサイトまでユーザーが来ない現象です。
「●●とは?」、「日本語の意味、英語のスペル」、「作り方、書き方」のような基本的な検索キーワードは生成AIに聞く方が正確でわかりやすく、検索結果のページを探す必要もないため、生成AIの回答で完結している状態なのです。これがゼロクリック検索であり、年々、このようなユーザーが増加しています。(本記事も「とは記事」に近いですが、狙いがありますのでご了承ください)
あるグローバル調査会社の結果では「生成AIの活用により●●年には検索エンジンの利用者が25%減と予想」と発表していますが、生成AIの進化は予測よりも早いです。
我々、マーケティング支援会社や担当者の間では、すでに「トラフィックは全盛期の30%減になっていて、アクセス数を減らさない戦い」という展開になっています。生成AIの活用によりサイトのトラフィックが減ることは必然として、リードの量と質を向上させていく方法に注力する方向転換を余儀なくされています。
そして、そこに登場したのがGoogleのAI モ-ド日本語版です。更に衝撃が続きます。
AIモ-ド(Google AI Mode)が日本に登場
AIモ-ドはGoogleが2025年5月にアメリカで発表されました。AIモ-ドとは従来のGoogle検索結果やリスティング広告とは別に、並列してAIの結果を表示する新しい機能です(Gemini 2.5 カスタム バージョンを使用)。
そして、日本語版は2025年9月9日に発表され、9月10日より利用できるようになりました。「AI Overview」もアメリカで発表され、5ケ月前後に日本でリリースされましたので、それより少し早いペースで実装されています。
-1024x576.png)
図1をご覧ください。Googleにいつも通り、検索ワードを入力し、AI Overviewや検索順位、リスティング広告の結果が出ます。本記事ではこれをGoogle通常モ-ドと呼ぶことにします。
Google通常モ-ドの検索の結果は‘すべて’ですが、その左に‘AIモ-ド’のタブが表示されます。これがAIモ-ドの機能であり、AIモ-ド回答になります。Googleトップ画面の「Googleで検索又はURLを入力」の右に、AIモ-ドの機能ボタンが表示されますので、そこから直接利用することもできます。
AIモ-ドのアメリカでの利用率はまだ3%前後と少なく、使い慣れている通常モ-ドがすぐになくなることはありませんが、注意が必要です。なぜなら、今後はAIエージェント機能が搭載されたり、AIモ-ドに広告が表示されたりすると利用率が一気に高まるかもしれないからです。
AI Overviewが搭載されたGoogle検索のゼロクリック率は約40%と言われています。しかし、AI モ-ドが搭載され、AIモ-ドだけを使っているユーザーのゼロクリック率 は約90%というデータも出ています。つまり、「生成AIで完結し、ウェブサイトを閲覧しない人」は9割存在するということです。
AIモ-ド利用率が上がれば、ゼロクリック検索率も相対的に上がります。自社のウェブサイトを閲覧してもらうためのコンテンツ作成、SEO対策、インバウンドマーケティングが大きく変わるかもしれませんので、今後も注視していきたいと思います。コンテンツ作成、SEO対策、インバウンドマーケティングに関する記事は下記をご覧ください。
引用元記事 インバウンドマーケティング 認知される最強施策を事例で解説
プロンプト一覧 一般企業は簡単な質問文を使う
これまでの生成AIのプロンプト=命令文や質問文は難しいイメージがありました。プログラミングやコーディングのような分野には専門的なプロンプトエンジニアが存在しますが、一般企業の利用ではプロンプトが難しいと生成AIの利用率は上がりません。次のような簡単な質問文を入力するケースが多いと感じます。MOFU・BOFU向けのプロンプト一覧でご紹介いたします。
MOFU・BOFU向けプロンプト
- ●●を構築してくれる会社を教えて
- ●●を支援してくれる会社を教えて
- ●●をサポートしてくれる会社を教えて
- ●●を導入してくれる会社を教えて
- ●●に強い会社を教えて
- ●●で人気がある会社を教えて
- ●●を定評がある会社を教えて
- ●●を知名度の高い会社を教えて
- おすすめの●●を教えて
【●●の例】
- 企業の課題・戦略・全般、製品、商品、サービス、アウトソーシング、コンテンツなど
このように●●に対して、「会社」や「製品・サービス」の良いものを教えて!と生成AIに簡単に聞いているユーザーが増えています。生成AIに質問した結果に、みなさんの会社や製品・サービスが引用元として表示されていれば、新しい問合せにつながるかもしれません。何か良い方法はないのでしょうか?
生成AIに選ばれる方法は何かないの?
生成AIの利用率は、ChatGPTやGeminiのような生成AIツールやGoogle検索のAI OverviewやAIモ-ドの種類を問わず、今後も増えていくことが予想されます。そうすると、ゼロクリック検索による自社サイトに来ないユーザーも増えていくため、サイトのトラフィックやアクセスは減っていきます。万全な対策は存在せず、なんとか維持するか微増減を続けていくしかないと言えます。
しかし、自社サイトへのトラフィックは減ったとしても、質の良いリードや問合せにつなげる考え方ややり方があります。詳しくご紹介していきます。
-1024x576.png)
図2をご覧ください。マーケティングファネルという考え方は、大きなファネルからリードを獲得して、ユーザーを育成していくプロセスがインバウンドマーケティングの王道です。わかりやすく整理するために、SEO向けとGEO向けのファネルをして表にしてみました。
| SEO向けファネルの進捗 | ウェブユーザーの状態 | キーワードや記事 | 育成するための施策 |
| TOFU (Top of Funnel) | 学習・情報収集 | Knowクエリ | ブログ・記事 |
| MOFU (Middle of Funnel) | 解決策を考えている | Doクエリ | ナーチャリングメール・ダウンロード資料 |
| BOFU (Bottom of Funnel) | 比較検討・選定する | Buyクエリ | ウェビナー・インサイドセールス |
これまでは、このようにウェブユーザーをTOFU→ MOFU→ BOFUに育成し進捗させることがインバウンドマーケティングの鉄則でした。これはこれで今後も重要なウェブマーケティングの施策です。
しかし、一気にBOFUユーザーにアプローチできる方法が増えました。それが生成AIに質問をするユーザーの回答の引用元(URLリンク)になるという状態です。
みなさんも生成AIを使っていたら、回答に引用元(URLリンク)があるケースとないケースが存在することはないでしょうか? 質問文や検索したい内容によりますが、Knowクエリ(とは?記事)は引用元が表示されず、生成AIの回答で完結できるケースが多いようです。
一方、DoクエリやBuyクエリには引用元が多く表示されるケースが多いと感じられます。
| GEO向けファネルの進捗 | ウェブユーザーの状態 | キーワードや記事 | 引用元の表示 |
| TOFU (Top of Funnel) | 学習・情報収集 | Knowクエリ | 少ない。生成AIで完結できるのでゼロクリック検索 |
| MOFU (Middle of Funnel) | 解決策を考えている | Doクエリ | 普通。生成AIとウェブサイト |
| BOFU (Bottom of Funnel) | 比較検討・選定する | Buyクエリ | 多い。生成AIに質問しウェブサイトで確認する |
総括すると、Knowクエリ(とは?記事)はある程度、生成AIで調べられるので生成AIで完結しウェブサイトに行く必要がないということです。このようなトラフィックが減ってきているので今後ウェブマーケティングには対策が必要です。
一方でDoクエリやBuyクエリも生成AIで一定の回答を得られますが、生成AIはたまにハルシネーション=ウソをつきます。会社の問題点の解決策を探したり、比較検討や選定をしたりしている際に、信憑性の低い情報で企業担当者が動くわけにはいきません。
企業担当者はDoクエリやBuyクエリの質問・回答に引用元(URLリンク)があれば、直接URLをクリックしウェブサイトで確認します。このような流れでMOFUユーザーやBOFUユーザーが自社サイトに流入してきているケースは、GA4を見ていると徐々に増えています。
「解決先を探している。比較検討・選定をしている」可能性の高いユーザーであるため、非常に質が高く、アプローチしてみると商談のアポが取りやすい状態なのです。
経営者はGoogleで検索して資料をダウンロードするケースは減ってきています。しかし一方で、経営者は生成AIの利用度が高いと言われています。ある調査結果では経営者の40%が、毎日利用しているというデータもあります。
このような生成AIを利用するユーザーを自社サイトに誘導する方法があります。それがGEO=生成AIに選ばれるためのマーケティング施策です。生成AIに質問文を入力した際に企業の製品・サービスが選ばれやすいようにサイトやコンテンツを最適化すれば、引用元となる自社サイトのURL・ソースを生成AIにリンクさせることができます。
では実際にどのような作業をすれば、生成AIに引用元を表示させて、ユーザーを自社サイトに誘導できるのでしょうか?まだ数少ないGEOのマーケティング事例からご紹介していきます。
GEOのマーケティング事例をご紹介
実際に弊社がGEO対策を行い、生成AIに選ばれた事例でご紹介いたします。一般的なユーザーがGoogleで検索したり、生成AIに質問したりするケースで進めていきます。
具体的なGEO事例 想定ケース
- MEDDPICC(メディピック)が、どんなものか調べたい
- MEDDPICC研修を提供している会社も知りたい
ちなみに本記事で意味や解説は割愛しますが、MEDDPICC(メディピック)とは、営業の新しいヒアリング項目でありフレームワークです。外資系企業で数多く導入されており、最近、注目されています。詳しくは下記記事をご覧ください。
引用元 MEDDPICC(メディピック)とは?外資系営業のフレームワークとして広がる理由
【想定ケース ユーザーの行動】
- Googleに「MEDDPICC」という検索ワードを入力して、調べる
- 弊社サイトが検索1位に表示される
-1024x576.png)
- MEDDPICC研修を提供している会社も知りたい
- ChatGPTに「MEDDPICCの研修ができる会社を教えて」と質問した
- ChatGPTの最初にラシックマーケティング社が回答され、引用元のリンクも表示された
-1024x576.png)
- ChatGPT-5の引用元から、自社サイトの営業研修サービスサイトに流入できた
- 実際にMEDDPICC研修の問い合わせが増えた
-1024x576.png)
しかし、GEO対策をするまでは生成AIに表示されなかった。なぜ、できたの?
図3から図5のようにサイトやコンテンツを最適化すれば、生成AIに選ばれました。図3にようにGoogle検索では1位表示を続けていたMEDDPICC記事だったのですが、当初は図4のように生成AIに選ばれていませんでした。
その理由は、重要である図5の「サービスページ」がしっかりとメッセージ化や構造化ができていなかったからです。そこで、実際に提供していた「MEDDPICC研修をやっています」と詳しく表記しました。その他のGEO作業も行うと、2日後には生成AI:ChatGPTに回答・表示され、引用元も表示されるようになりました。
「検索上位の記事に対するウェブクロールによって、生成AIの回答は60%が作成される」というデータもありますが、GEO対策に2日後にChatGPTの回答と引用元が表示されたのは、このデータを実証できたと感じています。
このように生成AIに質問文を入力した際に企業の製品・サービスが選ばれやすいようにサイトやコンテンツを最適化すれば、引用元となるソース、自社サイトのURLを生成AIにリンクさせることが実証できます。
ちなみに「MEDDPICC研修」は歴史が浅く競合他社も少ないため、生成AIの個別学習データからの回答ではないかもしれません。実績のある製品・サービスは、販売実績データやメーカーが発行するパートナー認定データから、回答や引用されます。生成AIの学習アルゴリズムはまだまだわからない部分が多いので、簡単なものではなく手探り状態と言えます。
しかし、生成AIを利用するユーザーを自社サイトに誘導する方法「GEO」は、これからの企業に必要な生成AIマーケティング施策です。試行錯誤を繰り返しながら、GEO対策を実践していくべきではないでしょうか?
7つのやり方に売上向上のヒントが隠されている
ラシックマーケティング社 サービス基本ガイド
GEO(生成AI最適化)でよくある質問
GEOのマーケティング手法に関するよくある質問と回答をご紹介いたします。
Q1 GEO対策のポイントを総括すると何が重要ですか?
答え ブログや記事で製品・サービスにつながるキーワードを検索上位にしておくことと(SEO)、製品・サービスページの強みをメッセージしてキーワードと連動させることがGEO対策の重要なポイントです。
Q2 GEO(生成AI最適化)のマーケティング支援を提供している会社はありますか?
答え ラシックマーケティング社が「インバウンドマーケティング(SEO+GEO)支援を提供しています。詳しくは次のページをご覧ください。https://rashic.co.jp/service/
まとめ
「GEOとは?生成AIに選ばれるマーケティング手法と事例を紹介 」と題して、ご紹介してまいりました。生成AIに対応するための基本から実践に至るまで、事例を交えてご紹介してきました。「よく言われるGEO対策の方法」に、下記のようなポイントが挙げられます。
- 構造化データにする → これはSEOでも同じであり基本
- LLMs.txtの設定 → すでに不要論が多数
- E-E-A-T強化 → 経験・専門性・権威性・信頼性はGoogle検索のアルゴリズムと同じ
- AIが好む文章 → 質問回答のようなFAQ方式というけど、ホント?
数多くの企業が手探りの状態で試行錯誤しているため、このようなGEO対策も必要かもしれません。しかし、本当に必要なGEO対策の中核は「コンテンツづくり」だと言えます。さいごに総括として、まとめてみます。
GEO対策の方法 総括
- 製品・サービスの強み・メッセージを明確にし、記事の中枢キーワードにする
- その記事をGoogle検索で上位にする
- メッセージやキーワードに沿った製品・サービスページを作る
その他にも細かなGEO対策はあります。しかし大事なのは、「とは?記事」のようなKnowクエリはこれから生成AIに任せて、みなさんの製品・サービスのど真ん中=良い部分やメリットをユーザーに訴える記事・コンテンツをしっかり作っていくことではないでしょうか?
そして、大切な考え方として「SEOの延長線上にGEOが存在する。SEOとGEOはセットで対策する」ということも忘れないでおいてください。
生成AIで検索したり調べたりするユーザーの利用率が、突然50%以上になるわけではありません。Google検索をする通常モードのユーザーはまだまだ存在するため、SEOを意識したコンテンツ作成やインバウンドマーケティングの作業は続けなければなりません。
しかし、マーケティング施策の潮目が変わる大きなターニングポイントを迎えているのは事実です。これから企業に求められる新しいマーケティング施策としてGEO対策をSEOと共に取り組んでいきましょう。また、GEOの新しい成功事例や対策方法が出てくれば、引き続きご紹介していきたいと思います。
- GEOとは?生成AIに選ばれるマーケティング手法と事例を紹介
- インバウンドマーケティング 認知される最強施策を事例で解説
- 【2022年最新】BtoBマーケティング事例 3つの面白い傾向を発見
- 営業ブログ ノウハウを新規開拓営業に使う、全く新しい方法
- プッシュ営業はやりすぎ注意!プル営業の質の良さを取り入れよう
- ブログを企業の人材育成へ使う方法 営業・マーケだけじゃない!
- ブログの始め方 営業・マーケティング新規活動の常識へ
- オウンドメディアとインバウンドマーケティングの違いとは?
- Google Search Console(サーチコンソール)の使い方とは?インバウンドマーケティングで使いこなすための見方
- Google Search Console(サーチコンソール)とグーグルアナリティクスの違いをインバウンドマーケティング視点から解説【初心者向け】
- 最強の新規開拓手法 インバウンドマーケティングに企業対応するためのポイントとは?
- どうすればインバウンドマーケティングと呼べるのか? 企業で使うための意味と手法を解説
- ブログを書けばインバウンドマーケティングと思っているあなたに~その事例と、まずやるべきことを解説~
- 伝わる製品キャッチに変えて新規開拓営業をやってみよう!