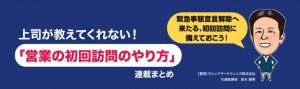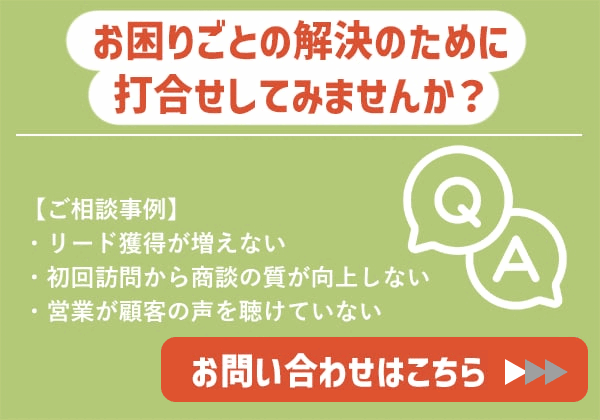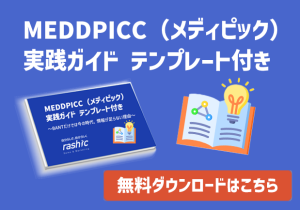仕組みと仕組みづくりという言葉があります。仕組みとはどんな意味で、ビジネスの仕組みづくりとはどのような作業をすれば構築できるのでしょう? そこで今、仕組みづくりがビジネスで求められる意味を解説しながら、ビジネスの仕組み作りを仕組み例でご紹介していきます。「仕組み」を理解していく上で、「組織と個人」「標準化と手順化」「仕組みとしくみ、仕組み化」の違いが大切なポイントになってくることがわかってきました。
目次
仕組みとは? 仕組みづくりがビジネスで求められる意味
仕組みとは、組織の役割と責任をツールとルールに落とし込んで、目的を達成するため回し続けられるシステムのことです。ビジネスでは仕組みを改善して、より良くしていくために標準化、組織文化や風土、体制も重要な要素です。仕組みづくりとはこのような内容を組織で構築するために取組みと言えるでしょう。
仕組みをもっと簡単に言うと「再現性の高い業務プロセス」ではないでしょうか? ビジネスの仕組みは主に「業務」で利用します。企業の各業務の目的を達成するためには、再現性を高くすることが重要です。
業務の役割と責任をツールとルールに落とし込んで、標準化すれば業務の質は向上します。日・週・月と業務をチームで回し続ければ、業務の目標を達成できるはずです。このような意味で企業は業務で仕組みづくりをしていきます。仕組みづくりは今、ビジネスで求められているのです。
仕組みを言い換えると? 仕組みとしくみの違い
仕組みをひと言で言い換える言葉はないと思います。なぜなら、前述したようにビジネスの目的を達成するために回し続ける理由や必要なモノが複雑だからです。従って、‘ビジネス活用での仕組み‘という言葉は非常に便利に使えるのです。
仕組みを言い換えるとすれば、ひとつだけ良い言葉があります。それは「しくみ」です。仕組みを‘ひらがな’しただけで意味は同じですが、ビジネス活用では難しい言葉を使わず、わかりやすい文字にすると組織に浸透すると言われています。つまり、柔らかいメッセージの方が組織に伝わるということです。漢字とひらがなで4種類の仕組みを記載します。
- 仕組みづくり
- しくみ作り
- 仕組み作り
- しくみづくり
「難しそう・・」と社員が感じ取らず、「取組みやすそう!」と簡単なイメージで伝えることが、様々なビジネス改善の取組みでは大切です。‘3.仕組み作り’は漢字が多く「とっつきにくいな・・」と社員が感じるかもしれません。
‘1.仕組みづくり’か‘2.しくみ作り’が「簡単そうだからやってみたい!」と社員に思ってもらいやすい表記と言えるでしょう。このような社員が感じ取るイメージや位置づけとして、仕組みとしくみの違いがあると感じています。本記事では「仕組みづくり」に統一して表記していきます。
もうひとつ重要なことは、仕組みづくりは組織で取り組むもので、個人で取り組むべきものではありません。なぜなら、仕組みづくりには必ず、標準化するべき業務やルール等が必要だからです。標準化とは組織に行うもので、個人で行う標準化は手順化と言われています。
つまり、「個人で仕組みづくりをしている」と言う人がいたとすれば、それは「個人で手順化をしている」と言い換えられます。個人の手順化もとても良い取組みで、目的を達成するために改善をしながら、個人で回し続ける方法を持っていると言えます。
しかし、仕組みづくりはもっと複雑であり、組織の数多くの業務改善のために取組み、社員個人に実行させるべきものなのです。標準化と手順化の違いの詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
標準化、平準化、手順化の違いとは?マーケや営業業務に求められること
次に説明する案件管理の補足説明は、下記の記事をご覧ください。
ビジネスの仕組み作りをやっていこう 仕組み例でご紹介
仕組みとは、組織の役割と責任をツールとルールに落とし込んで、目的を達成するため回し続けられるシステムと定義しました。そして、ビジネスでは主に業務に仕組みづくりが活用されます。企業の中には人事・総務・経理等の管理業務、設計・生産・製造等のものづくりの業務など数多くの業務が存在します。
その中で今回は営業業務にスポットを当て、仕組みづくりの例をご紹介していきます。まず、仕組みづくりで営業が達成したいことや狙いから整理していきます。
営業の仕組みづくり例 案件管理
- 目的 新規案件を増やし、案件確度を適切に管理し、受注実績を向上させるため
- 責任者の役割と責任 案件を管理し、毎月のチーム受注予算を達成させること
- 営業の役割と責任 新規案件を創出し、提案により案件確度を進め、毎月の個人受注予算を達成すること
- ツール 営業支援システム(SFA/CRM)
- 会議体 案件管理ミーティング 毎週月曜9:00-10:00に開催(以下、ミーティング)
- ルール
- 案件の最新状況をツールに入力し、案件状況をミーティングで営業個人が報告する
- 新規活動状況をツールに入力し、新規案件の発掘状況をミーティングで営業個人が報告する
- 活動目標と実績、受注予算と実績状況を報告する
- ミーティングはリアル開催と対面で行う。リモート参加は基本NG
- 最終週月曜のミーティングでは、当月末の営業個人の受注見通しを報告する
- その報告をもって、責任者は会社に対し、チームの受注見通しと達成率を報告する
- 第2週月曜は10:00-11:00まで延長し、マーケティングチームと営業企画チームも参加し、新規施策の知恵だしディスカッションミーティングを行う
案件管理の仕組みづくり例としては、このように目的・責任と役割・ツール・会議体・ルールを標準化します。そして、これら全体が自然と毎週まわることがシステムなのです。ITを使った案件管理システム等もシステムのひとつですが、目的を達成するために組織で回し続けられることもシステムの一種です。
そして、なかなか営業が入力しない営業支援システム(SFA/CRM)の活用状況や達成率などのレポートで支援する営業企画や、新規案件創出のための施策を一緒に考えて実行するマーケティングチームの体制づくりも重要です。
「個人が営業数字をコミットする。そのために新規営業活動もする」という組織風土、責任者もマネジメントだけでなく、現場に降りて営業と一緒に考え、活動するという組織文化も大切です。
さらに仕組みは一回つくったら終わりではありません。仕組みをより良くしていくために改善していくために、責任者が気づき、個人が提言してどんどん良い仕組みに変えていかなければなりません。
営業の案件管理を例に挙げましたが、企業内の業務すべての仕組みづくりも同じことが言えます。例に挙げた案件管理の仕組みづくりのような内容を業務別に組織で構築し、ビジネス活用して実践していけば、仕組みづくりは強力な武器になると言えるでしょう。
そして、完全に回し続けられる企業の武器になった時に、ひとつの業務の仕組み化が出来上がったと言えます。仕組みづくりを実践し、仕組み化まで到達できる組織を目指しましょう。
7つのやり方に売上向上のヒントが隠されている
営業・マーケティング 7つのやり方 サービス基本ガイド
まとめ
「仕組みづくりとは?ビジネス活用の意味を理解して実践しよう」と題して、ご紹介してまいりました。仕組みと仕組みづくりがビジネスで求められる意味がご理解いただけたと思います。
組織で取り組むものが仕組み(標準化)であり、個人で取り組むことは手順化です。仕組みもしくみも柔らかい表現の差であり、大きな違いはありませんので、企業にとって根づく言葉を選んでいきましょう。
ビジネスの仕組み作り、仕組み例は営業の案件管理をご紹介しました。すべての業務の仕組みづくりに活用できますので、重要な項目をさいごに記載いたします。仕組みのフレームワークとしてぜひ、活用してみてください。
仕組みのフレームワーク
- 仕組みづくりの名称(柔らかい表現)
- 目的
- 責任者の役割と責任
- 業務担当者の役割と責任
- 活用するツール
- 会議体・ミーティング
- 本仕組みのルール
そして、仕組みを支援する体制と、組織文化や風土を合わせ、ずっと回る続けるシステムを構築すると、仕組み化に到達できます。ビジネスの目的を達成しやすくする、仕組みづくりと仕組み化を目指して、様々な業務課題に取り組んでいきましょう!
- PDCAサイクルは古い?時代遅れ?新しく代わる手法をご紹介
- 予算策定の「結局○○予算!」から脱却し達成する方法をわかりやすく解説
- 仕組みづくりとは?ビジネス活用の意味を理解して実践しよう
- 進捗管理の定義で営業とプロジェクトを見える化できる
- マジか?の意味 マジ3段活用を若者言葉から学ぼう
- 情報共有とは?できる人と組織が考えるメリット 方法と対策も解説
- 風呂敷を広げる人と畳む人の種類 ビジネスでどれがいいの?
- ソリューション営業 IT業界とコンサルティング企業に求められる要素
- 計画営業になろう!3週先を3つの思考で考えると3割増しになるよ
- ロジックの意味とは?ビジネスではストーリーも必要な理由 事例もご紹介
- 外回り営業 1回目から2回目に進めない人、進める人の差とは?
- ずっと社内にいる営業から脱却する・させる方法
- 若者言葉 7つの‘やばい’ 良い意味と悪い意味を知ろう!
- ニーズあります!って顧客ニーズをちゃんと説明できますか?
- BtoBで顧客単価と案件単価を上げる方法 奇策はないが秘策あり
- 受注確度やランクを定義すれば受注率が上がる その理由
- 時間がないと言う営業と、そうは思わない営業の差とは?
- 営業の不正事例 不合理な目標達成のための営業リスクと対策
- 営業失注 「値段で負けました」から「営業負けでした」と言える成長力
- MEDDPICC(メディピック)とは?外資系営業のフレームワークとして広がる理由