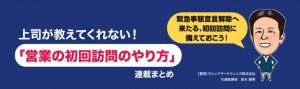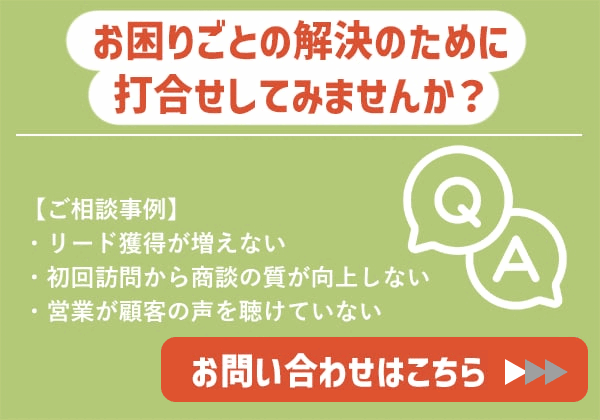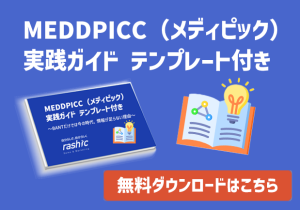営業組織では商談・案件を受注につなげるための進捗管理を実行します。システム開発や建設業のプロジェクト成功のための進捗管理を企業で取り組んでいます。しかし、営業や技術者からの報告の精度にバラツキがあったり、組織で進捗率の基準がなかったりしていることが原因で、進捗管理がうまくいっていないケースがあります。
進捗管理を正しく行うためには、進捗の定義が重要です。そこで、進捗管理、プロスペクト管理、ステージ管理、案件管理、パイプライン管理、確度管理の違いをご説明しながら、営業とプロジェクトの進捗管理の定義例をご紹介していきます。進捗管理の定義を組織ですれば、営業とプロジェクトを見える化できます。本記事を読んで、一緒に取り組んでみましょう。
目次
進捗管理とは?なぜ進捗率や状態の定義が必要なの?
進捗管理とは計画と実績を円滑に進めていくために、プロジェクトや営業等の状態を示した指標を作り、マネジメントしていくことです。進捗管理が組織に必要な理由は、そのプロジェクトや営業が前に進んでいるのか? 後ろに進んでいるのか? 何%の状況にあるのか?等の現在の進捗を正確に見える化するためです。
例えば、営業の商談や案件化の進捗がわからなければ、今月の売上がどれぐらい計上できて、半期の受注実績がどこまで達成できるのか把握できません。進捗管理をシンプルに言えば、企業の様々な計画を達成するために、その状態をできるだけ正確に見えるようにしていく手法です。
進捗管理の対象になる代表格が、営業の商談や案件とシステム開発や建設業等のプロジェクトです。営業は事業を続けるために大切な要素である受注や売上、システム開発や建設業等は受注後に完成させ、検収から入金につなげるためのプロジェクト進捗を管理していきます。営業の商談・案件・プロジェクトがどのような状態になるのかを把握することは、企業にとっては重要なマネジメントと言えます。
プロスペクト管理とステージ管理の違い 案件管理やパイプライン管理は?
進捗管理の定義の説明をしていく前に、その他にも似たような言葉があります。プロスペクト管理とステージ管理の違いや、案件管理やパイプライン管理という言葉です。これらの違いについて、まずは整理していきましょう。どれも営業に関する管理手法と言えますので、営業視点で説明していきます。
プロスペクト管理
英語のProspectは見通しという意味ですので、マーケティング視点ではリードから商談・案件までの見込み客というニュアンスです。スタートアップ企業や外資系企業ではプロスペクト管理という呼び名を組織で使うケースが多いように感じます。営業でプロスペクト管理を使う場合は、「見通しを立てるための案件管理」でよいと思います。
ステージ管理
英語のStageは場所という意味ですので、商談や案件の現在の場所をステージという呼び名で示した管理手法です。進捗管理がC→B→Aや50%→80%→100%のような進捗率で定義されること多い反面、ステージ管理Stage1→2→3→4→5は「現在の具体的な状態を示す方法」と言えます
案件管理
プロスペクト管理に近い管理手法であり、「見通しを立てるための案件管理」でもあるため、同じ意味だと言えます。英語で表現するか、日本語で表現するかの差と言ってもよいと思います。
パイプライン管理
営業の活動や商談・案件をひとつの棒グラフのようなパイプに見立てて表記し、管理や分析を行う管理手法です。詳しい内容は下記記事をご覧ください。
確度管理
進捗や進捗率を確度と言い換え、確度C→確度B→確度Aのように見える化していく管理手法です。詳しい内容は下記記事をご覧ください。
出典元 商談化と案件化の定義、違い、平均率とは?これであなたのチームは確度管理ができる!
プロスペクト管理とステージ管理の違いや、案件管理、パイプライン管理、確度管理は、このようなの違いがあると言えます。進捗管理の呼び方は企業風土に根づいていれば、なんでもよいと思います。大事なことは呼び方ではなく、進捗の定義を決めることです。
この進捗の定義ができていない企業は意外に数多くあります。そこで、営業の進捗管理の定義例とプロジェクトの進捗管理の定義例をご紹介していきたいと思います。
営業の進捗管理の定義
進捗の定義は、商談や案件の現在の正確な状態を示すものでなければなりません。まず、進捗状況と営業活動が一緒になっている企業があります。例えば、進捗状況がデモ・プレゼンになっているような状態です。デモ・プレゼンは営業活動であり、進捗状況でありません。
また進捗の定義に、営業が聴けた情報収集項目を当てはめるやり方もあります。BANT(B予算、A決裁者・意思決定者、Nニーズ、Tタイミング )やMEDDPICCが代表的な情報収集の方法です。詳しくは下記記事をご覧ください。
出典元 自動車営業のサシミとは?進捗と活動を一緒しない管理方法
出典元 MEDDPICC(メディピック)とBANTとは?外資系営業のフレームワークとして広がる理由
まずは営業の進捗管理の定義をご紹介していきます。
進捗率や進捗用語の例
- 見込みC →見込みB →見込みA →受注
- 確度C →確度B →確度A →確度S(受注)
- Stage1→2→3→4→5
進捗管理の呼び方は企業風土に根づいていれば、なんでもよいと思います。何度も申し上げますが、大事なことは進捗の定義を決めることです。では、どのように進捗の定義を決めていけばいいのでしょうか? 進捗の定義に用いると「管理しやすくなる要素」は下記のような例が挙げられます。
進捗の定義に用いる要素
- タイミング
- 情報収集に基づいた事実
- 客観的な状態
- 営業が感じること(主観)
- 営業の責任・決意・覚悟
このような進捗の定義に用いると、管理しやすくなる要素があります。ではこれらを取り込んで、進捗の定義を決めていく例を見ていきましょう。
進捗の定義 例1 タイミングと現在の客観的な状態
- 確度D(商談化) 1年以内には検討を開始し、自社に関心を示している状態。受注確率は無し
- 確度C(商談化) 6ケ月以内には具体的な検討が始まり、ニーズは高い状態。受注確率は無し
- 確度B(案件化) 3ケ月以内に結論を出す状態で、60%の受注確率
- 確度A(案件化) 1ケ月以内に契約できる状態で、80%の受注確率
- 確度S(契約中) 正式に合意し、契約手続き中の状態
進捗の定義 例2 BANT+Cの情報収集に基づいた事実とタイミングから
- Stage1 1年以内には検討を開始し、自社に関心を示している状態(T:把握)
- Stage2 6ケ月以内には具体的な検討が始まり、ニーズは高い状態(T・N:把握)
- Stage3 3ケ月以内に結論を出す状態で、50%の受注確率(T・N・A・B:把握)+技術要件とビジネス要件把握
- Stage4 1ケ月以内に契約できる状態で、80%の受注確率(C:競合他社の把握)+決裁プロセスにあがる状態
- Stage5 正式に合意し、契約手続き中の状態
このように進捗の定義に用いる要素である、「タイミング」「情報収集に基づいた事実」「現在の客観的な状態」を組み合わせると進捗管理がやりやすくなります。しかし、外資系企業などがMEDDPICCの「情報収集に基づいた事実」を取り入れて確度管理をしますが、複雑すぎて営業が混乱することがよくあります。あまり、情報収集項目を複雑にしないようにしましょう。
進捗の定義にはある程度、「営業が感じること(主観)を取り込む」が入っていいと思います。例えば、「80%の受注確率」というのは、「タイミング」「情報収集に基づいた事実」「現在の客観的な状態」だけでは判断しにくいものです。「営業の感じ方」を入れて、より精度の高いものにしていくと良いでしょう。
そして、「この案件は来月には決まると思います」「今月には決めます」と「営業の主観」だけでなく、「責任や決意」も入れて、営業が感じるのはとても良いことです。
「営業が感じる、そして責任も持つ」という狙いも確度管理に入れると、現場視点の感覚が研ぎ澄まされ、経験値から判断できる営業に成長していきます。「確度と覚悟(かくど と かくご)」は連携しているとも言えますね。
しかし、すべてが「営業の主観」から判断されてはいけませんので、このような項目を組み合わせながら、進捗管理を見える化していきましょう。
プロジェクトの進捗管理の定義 例
システム開発や建設業等のプロジェクトの進捗管理の定義は営業と違って、より客観的な「現在の客観的な状態」が優先されます。なぜなら、受注後の進捗管理は受注した企業・提供するベンダー側が立てたプロジェクト計画に沿って、工程・タスクを進めていかなければならないからです。
技術者が「今、進捗率は80%ぐらいです」と主観で報告して、ずっと進捗率80%で止まってしまうケースがあります。これは「80%シンドローム」と呼ばれる悪い進捗管理です。このようなケースを防ぎ、プロジェクト計画通りにプロジェクトを進めていく、客観的な状態を積み上げる進捗管理が必要なのです。
進捗の定義 例3 プロジェクト要件定義の工程
- 未着手 0%
- ヒアリング着手 10%
- ヒアリング完了 40%
- 要件定義書作成 70%
- プロジェクトリーダー レビュー実施・完了90%
- プロジェクトマネージャー最終承認 100%
進捗の定義 例4 システム開発の工程
- 未着手 0%
- 着手 10%
- プログラム完成 60%
- 最終テスト完了 80%
- プロジェクトリーダー レビュー完了100%
営業が一人で報告していく商談・案件の進捗管理に比べて、プロジェクトの進捗の定義は、多くのプロジェクトメンバーが関与し、数多くの報告があります。従って、「現在、このような状態にあります」という客観的な状態の報告を積み上げることによって、正確な進捗が把握でき、プロジェクトを見える化できるのです。
まとめ
「進捗管理の定義で営業とプロジェクトを見える化できる」と題して、ご紹介してまいりました。進捗管理の重要性と、進捗の定義が必要な理由がご理解いただけたと思います。
プロスペクト管理、ステージ管理、案件管理、パイプライン管理、確度管理の微妙なニュアンスの違いも整理してみました。どの管理方法も「組織で状態を把握したい」という目的は同じですので、企業カルチャーに合った管理手法を採用してみましょう。
営業の進捗管理の定義例、プロジェクトの進捗管理の定義例をぜひ、参考にしてみてください。最近の弊社事例では、営業チームの商談・案件の進捗管理の定義を決めていくケースが多いです。その背景には次のような営業現場の問題点があると感じています。
進捗管理 営業現場の問題点
- 組織で定義が決まっておらず、営業の主観に任せている
- 営業の決意から「今月には結論は出ます」の報告を鵜呑みにしたら、受注予定月がズレた
- なんとなく進捗の定義は決まっているが、上司がしっくりこない。
- 営業によっても微妙に精度が違う
そして、エクセルではなく、SFA/CRMで進捗管理をしていく組織が増えています。進捗の定義を組織でしっかり行い、SFA/CRMを正しく上手に見える化と活用をしていきましょう。
- PDCAサイクルは古い?時代遅れ?新しく代わる手法をご紹介
- 予算策定の「結局○○予算!」から脱却し達成する方法をわかりやすく解説
- 仕組みづくりとは?ビジネス活用の意味を理解して実践しよう
- 進捗管理の定義で営業とプロジェクトを見える化できる
- マジか?の意味 マジ3段活用を若者言葉から学ぼう
- 情報共有とは?できる人と組織が考えるメリット 方法と対策も解説
- 風呂敷を広げる人と畳む人の種類 ビジネスでどれがいいの?
- ソリューション営業 IT業界とコンサルティング企業に求められる要素
- 計画営業になろう!3週先を3つの思考で考えると3割増しになるよ
- ロジックの意味とは?ビジネスではストーリーも必要な理由 事例もご紹介
- 外回り営業 1回目から2回目に進めない人、進める人の差とは?
- ずっと社内にいる営業から脱却する・させる方法
- 若者言葉 7つの‘やばい’ 良い意味と悪い意味を知ろう!
- ニーズあります!って顧客ニーズをちゃんと説明できますか?
- BtoBで顧客単価と案件単価を上げる方法 奇策はないが秘策あり
- 受注確度やランクを定義すれば受注率が上がる その理由
- 時間がないと言う営業と、そうは思わない営業の差とは?
- 営業の不正事例 不合理な目標達成のための営業リスクと対策
- 営業失注 「値段で負けました」から「営業負けでした」と言える成長力
- MEDDPICC(メディピック)とは?外資系営業のフレームワークとして広がる理由