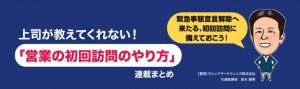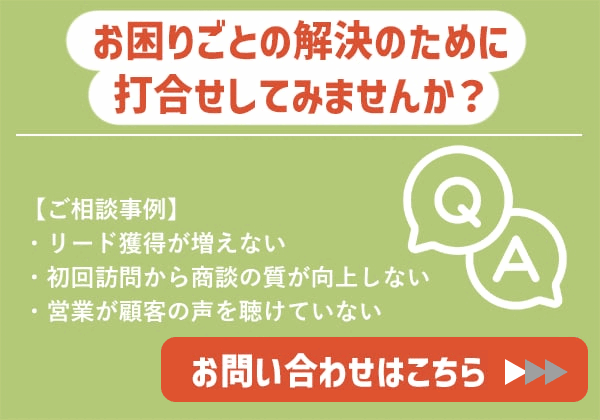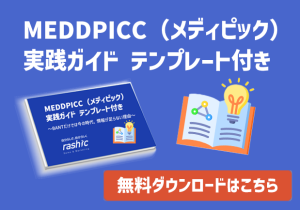ビジネスシーンでは聞く、訊く、聴くの違いを理解し、使い分けないといけないと言われています。ところが先日、「営業が聞かない、訊けていない、聴くことができない場面」に多数、直面しました。なぜ、このような状況になってしまうのでしょうか? 今の営業は指導してもしっかり話は聞きますし、素直で一生懸命です。しかし、商談中に訊いたり聴いたりする姿勢には、いくつかのヒアリングポイントがあります。そこで、訊けていない理由を分析しながら、営業が訊けるようになり、聴くことができる方法を解説していきます。
目次
ビジネスで聞く、訊く、聴くの違いとは?
ビジネスで聞く、訊く、聴くが大切と言いますが、それぞれの意味と違いをご存知でしょうか。
訊くとは
尋ねたり、質問したりすることです。ビジネスで顧客に訊きたい時に使います。
聞くとは
自然に耳に入ってくることです。ビジネスで商談や会話している時に使います。
聴くとは
積極的に耳を傾けることですので、ビジネスでは営業ヒアリング時に使います。
これが訊く、聞く、聴くの違いです。すべてまとめて「聞く」でもいいかもしれませんし、「ここまで細かく分けられても、覚えられない・・」という声が聞こえてきそうです。
しかし、商談時に訊く、聞く、聴くができていない営業が多いと感じています。弊社はマーケティングや営業支援サービスを提供しているので、先日かなりの数の商談に同行する機会がありました。様々な目的やチェック項目がありましたが、私のひと言目は「今の営業は訊けていない」という感想でした。驚くほど、訊けていない今の状況を振返り、分析してみました。
今の営業は聞かない、訊けていない、聴く気がない その理由
「今の営業は訊けていない」という感想をもう少し深掘りすると、「今の営業は聞かない、訊けていない、聴く気がない」と言えます。少し言い過ぎで一刀両断しているかもしれませんが、これぐらいの表現をしていいぐらい訊けていないと思います。ちなみに今の営業とは、若手営業もいますし、かなりのベテラン営業も含みます。この数年の営業スタイルと認識ください。
今の営業は、説明したり指導したりすれば話はしっかり聞きますし、素直です。学ぶ姿勢は積極的で、勉強するためには聞きます。しかし、商談で聞かないのです。そして、訊けていないですし、聴く気がないとも感じるのです。
なぜ、聞かない、訊けていない、聴く気がないのか、かなりの数の商談に同行した結果を分析してみました。前提はIT営業が自社の業務ソフトをリモート商談で1時間ほど説明しているシーンをイメージしてください。訊けていない=質問ができていない、その理由を整理しました。
訊けていない理由
- 機能を一生懸命に話すことに終始しているから
- リモート商談なので、顧客に質問時間を早めに与えると、会話が終了してしまいそうだから
- つまり、顧客から質問がないのが怖い
- 営業がこうやって受注したいという想いやシナリオがないから、営業から質問が出てこない
- 組織で決められた訊くべきことが決まっていない
- 顧客志向ではなく、内向き志向だから(視点が自社向き)
このような訊けていない理由、分析結果になりました。この中で「組織で決められた訊くべきことが決まっていない」があります。情報収集項目が決まっていないのは、組織のせいです。営業チームでリモート商談・初回商談で訊くべきことを決めましょう。
詳しくは下記記事をご覧いただき、みなさんもBANT営業(バント営業)やMEDDPICC営業(メディピック営業)を目指してください。本記事では、組織で取るべき情報収集項目が標準化されている前提で、ご説明を続けていきます。
BANT営業(バント営業)・MEDDPICC営業(メディピック営業)の情報収集項目を学べる記事
MEDDPICC(メディピック)とは?外資系営業のフレームワークとして広がる理由
そして、訊けていない理由で最も注目したいポイントは、「リモート商談は顧客に質問時間を早めに与えると、商談が終了してしまいそうだ。つまり、質問がないのが怖い」という点です。
最近では営業の初回商談のほとんどは、リモート商談になっています。このリモート商談が訊けていないポイント、鍵になっていると感じました。
訪問によるリアルな商談よりもリモート商談は、情報量が落ちます。情報量とは1時間の商談の中で、製品説明に対する顧客の反応、理解しているか? の状況確認など、ちょっとしたしぐさのことです。このような情報量はリアル商談よりもリモート商談の方が確実に少なくなってしまいます。
つまり、商談中に感じることが減っているのです。このため、「この部分の説明がわかりにくかったですかね?」という情報はほとんど入ってきません。しかも、最後に「質問はありませんか?」という時間は取るものの、質問がなければ商談が終わってしまうので、ついつい少ない質問タイムになってしまいます。商談1時間のうち、残り15分から10分ぐらいで質問タイムに入った営業がほとんどでした。
説明中に細かく分けて「ここまでで質問はありませんか?」と工夫している営業もいました。しかし、商談の前半は盛り上がらないので質問は出にくいものです。「これからまだ説明があるだろう」と思っている顧客は、すべて理解してから質問という姿勢のため、途中質問が出にくいのです。
いったん、訊けていない重要ポイントをまとめます。
- 途中で訊いても質問は出にくい
- 顧客の反応がわかりづらいのがリモート商談の特徴なので、従って情報量が少ない
- 早めに質問タイムに入ると、顧客から質問がないので商談が終了してしまいそうな雰囲気になる
- やっぱり、顧客から質問がないのが怖い
これでは顧客の声に耳を傾ける「聴く」まで到達もできておらず、聴く気がないと言われても仕方がありません。では、どのようにすれば訊けるようになり、聴くことができるのでしょうか?
7つのやり方に売上向上のヒントが隠されている
営業・マーケティング 7つのやり方 サービス基本ガイド
営業が訊けるようになり、聴くことができる方法
リモート商談で営業が訊けるようになり、聴くことができる方法はいくつかありますが、すぐできる方法を大きく2つお話します。
1つ目の方法は、リモート商談の半分の時間は見込み顧客に渡すことです。1時間のリモート商談であれば、思い切って30分で機能説明を終了させ、30分を顧客が質問する時間に渡してください。
「いやいや、途中質問もなく、顧客の反応などの情報量も少ないのに、商談が終わってしまいますよ」という声が聞こえてきそうですが、ズバッと半分、渡してみてください。このやり方の方が、意外に質問が出てきます。
顧客は困っていることを聴いてほしいものです。「ご質問はありませんか?今、困っていることでもいいのでお聞かせください」と言えば、顧客は口を開き、現在の問題点を話し出します。製品説明の質問を訊こうとするから、質問が出てこないのです。まずは、顧客のお困りごとに対して、聴く=耳を傾けてみましょう。あっと言う間に、30分が顧客と営業の会話で盛り上がって、終了することはよくあります。
しかし、「困っていることをお聴きしたいです」と言っても、あまり話してくれない顧客もいます。 そこで2つ目の方法です。顧客が30分の質問タイムで話してくれなければ、営業が話せばいいのです。こちらから説明の続きを話しながら、訊いていけばいいのです。ただし、また機能に関する説明をしてはいけません。
例えば、「弊社の顧客はよくあるお困りごとに対して、こうやって解決していますよ」「解決策にはこんな導入事例やユースケースがありますよ」と、お困りごとを引き出すために営業が話すのです。顧客が訊きたい内容や聴きたくて困っていることを、営業が引き出していくのです。
製品で顧客の困っていることを解決した事例を、営業がいくつか説明していけば、顧客のお困りごとを喚起できます。その瞬間、顧客が口を開きます。そうなれば、営業が訊けるようになり、聴くことができます。
リモート商談の「質問がでない。終わってしまいたくない!」という恐怖もなくなり、むしろ後半の30分は大盛り上がりし、2回目以降の商談化や案件化につながりやすくなるのです。
「半分の時間は見込み顧客に渡す」「顧客が話さなければ、営業が引き出すためのトークをする」この2つの方法は私も意識してやっています。ぜひ、みなさんもビジネスで訊く、聞く、聴く営業になるために、実践してみてください。
リモート時代の今、話すことに注力して、聴けていない営業が増えていると感じています。営業は顧客の声を聴いてこそ、課題解決の提案が始まります。そこで、聴ける営業になるための方法をご紹介いたします。
「聴ける営業になろう!」研修資料抜粋版
~聴くと、会話につながる、関係構築できる~
弊社の「聴ける営業になろう!」の研修資料から抜粋した内容をご紹介しています。ぜひダウンロードいただき、聴ける営業の組織づくりを考えてみましょう。
まとめ
「ビジネスで訊く、聞く、聴く 営業はできていますか?」と題して、ご紹介してまいりました。ビジネスシーンでの聞く、訊く、聴くの違いがご理解いただけたと思いますし、強めの表現になってしまいましたが、今の営業は聞かない、訊けていない、聴く気がない理由も把握できたと信じております。
訊けていない、聴くことができないポイントはリモート商談の顧客の反応のなさにありました。営業も機能を一生懸命に説明するだけではなく、また質問がない恐怖を感じずに、半分の時間は見込み顧客に渡してみましょう。
営業が訊けるようになり、聴くことができる最大の方法は「営業が話しながら、お困りごとや質問を引き出すスキル」です。製品の説明を内向き志向でやらず、顧客志向で説明しようとすれば、自然とできるスキルです。
「弊社の顧客はよくあるお困りごとに対して、こうやって解決していますよ」
「解決策にはこんな導入事例やユースケースがありますよ」
このような説明を話しながら質問タイムを営業が主導権を取って進められるスキルがあれば、質問が出なくても怖くありません。顧客のお困りごとをどんどん引き出せるようになり、1時間で収まらないぐらいリモート商談が盛り上がります。ぜひ、実践してみて、訊けるようになり、聴くことができる営業を目指してください。
- ヒアリング力を高めよう!営業とエンジニアに必要なスキルを紹介
- 営業研修でスキルアップしよう!言語化されたノウハウを学ぶ
- 競合他社に勝つ3つの施策 調査・分析・資料・プレゼンで差をつけよう
- ビジネスで訊く、聞く、聴く 営業は実践できていますか?
- 報連相ができない人と上手い人の違い 営業提案力と比例する
- 意思決定者(DMU)に向かっていかない営業、動く営業の違い
- セールスと営業の違い 英語と日本語の良さをビジネスに活かそう
- 営業マインド 方法論だけでなく精神論も欲しがる若者の気持ち
- 課題解決型営業こそソリューション営業 提案方法を例で5つご紹介
- 営業の事前準備をよくわからないまま活動してきたあなたに 大切な3つの理由を紹介
- 雑談力を営業が高めるために 入り方やネタを例でご紹介
- 自動車営業のサシミとは?進捗と活動を一緒しない管理方法
- 標準化、平準化、手順化の違いとは?マーケや営業業務に求められること
- 営業企画と営業推進の仕事は面白くて、効果は絶大!部門を作ろう
- 営業予算の組み方や立て方とは?作り方までやってみよう!
- 顧客志向とは?顧客志向経営からマーケティングと営業を実践しよう
- 営業インセンティブと評価方法 有名企業の事例もコッソリご紹介
- IT営業やシステム営業はいらない?きつい?難しい?将来性?にお答えします
- 営業トークのコツ 3つのポイント つかみ・雑談ネタの基本セット
- 営業トーク・営業話法 課題と言わず、問題と言う意味とは?