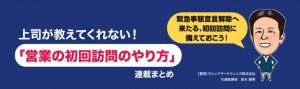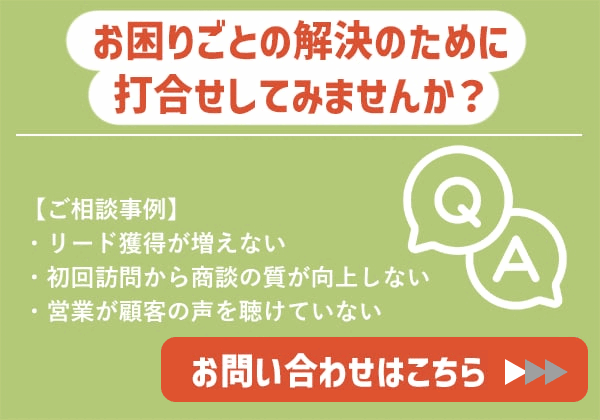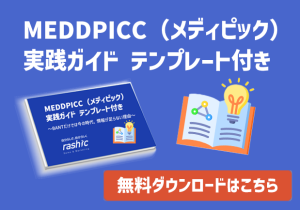ビジネスシーンでヒアリングをする機会は数多くあります。「顧客を理解するために顧客の声を聴く」という作業ですが、受注前と受注後のヒアリングでやり方は大きく変わってきます。どのようなポイントを意識し、どんな勉強や活動をすればヒアリングができるようになるのでしょうか? そこで、ヒアリング力を高めるための方法やテクニックを解説していきます。「聴く力」の専門性を高めるためのヒアリング 研修もご紹介いたします。
目次
ヒアリングとは?営業ヒアリングとは少し違う
ヒアリングとは顧客のニーズ=欲求を聴き出し、現在の課題、要求したいこと、必要性の有無を明確にすることです。英語のHearingを調べてみると聴覚や聴くという意味が出てきます。
Hearingには聞くことという表記も出ますが、聞くと聴く、そして傾聴には大きな違いがあります。これらの違いはヒアリングに大切な要素ですので、理解していただくと本記事の狙いがわかりやすくなります。
- 聞く 自然の耳に入ってくること ※訊く 訊ねること
- 聴く 積極的に聴くこと
- 傾聴 徹底的に聴くこと
営業が顧客にヒアリングするケースを営業ヒアリングと呼びます。営業ヒアリングはその名の通り、営業が顧客に聴くわけですが初回訪問や簡単なヒアリングを指すイメージです。例えば、BANTのB(バジェット)=予算、A(オーソリティ)=決裁者、T=タイミング、そして簡単なN=ニーズを聞くような商談では営業ヒアリングと呼びます。
しかし、ヒアリングの本質とは顧客のニーズ=欲求を聴き出すことです。現在の課題、要求したいこと、必要性の有無を整理して明確にする作業が重要です。そして、提案書にまとめ、顧客に課題解決を提案していきます。IT業界であれば、営業だけでなくエンジニアと呼ばれる技術・開発メンバーも同席して聴きます。これが本来、ヒアリングと呼ばれるものと私は考えています。
営業ヒアリングとヒアリングは同じような意味で使用されますが、このように少し違うポイントがあるのです。本記事では営業とエンジニアがヒアリング力やスキルを高める方法をご紹介していきます。
ヒアリングとヒヤリングはどちらが正しいの?
ヒアリングと記載してきましたが、ヒヤリングという表記や言い方もあります。これらは「ア」と「ヤ」の違いでどちらも母音が「あ」のためは、自分で話していても「ヒアリングとヒヤリング、どっちで言っているかな?」と私も振り返ったほどです。どちらが正しいのでしょう?
ヒアリングとヒヤリングはどちらの言い方も表記も正しいのですが、一般的にはヒアリングが記載されるケースが多いようです。耳で聞いていても、どちらも似ているので区別しにしくいと思います。Hearingを日本語にした場合、本記事ではヒアリングの表記で統一して記載していきます。
ここまで記載してきたヒアリングに関する詳しい内容は下記記事をご覧ください。
訊く・聞く・聴くの違い
記事 ビジネスで訊く、聞く、聴く 営業は実践できていますか?
傾聴力
記事 営業傾聴力と営業ヒアリングはどう違うの?課題整理をするための使い方
ニーズ=欲求
記事 ニーズあります!って顧客ニーズをちゃんと説明できますか?
要件定義やプレサポートで、顧客を理解しニーズを把握するために聴いてみよう
ヒアリングとは、時間をかけて営業とエンジニアが顧客の声を聴くことです。顧客の声とは、主に顧客のニーズ=欲求を聴き出すことです。ニーズ=欲求とは課題、要求、必要性の3つに区別され、3つすべてが揃う時もあれば、1つや2つの場合もあります。
ここで大切なポイントは「時間をかける」ということです。そして、「受注前」と「受注後」によっても時間のかけ方は、営業・エンジニアの提案側視点と顧客視点の双方で変わってきます。それぞれのヒアリングの進め方を整理してみましょう。
ヒアリングの進め方 受注前
「受注前」なら、提案側も顧客も「まだ発注するかどうかわからない」という意識が働きます。顧客は「まだ御社に決めたわけではない」と思いますし、提案側は「受注したいけど、最小限の時間のかけ方で進めたい」と思います。IT業界ではプレサポートと呼ばれる、提案段階の営業をエンジニアが支援するケースです。主に初回訪問の次のフェーズが該当します。
「次回はいろいろと現状業務や課題についてお伺いしたいので、お時間をいただけますか?」と顧客に合意できた次のフェーズがヒアリングです。これは1時間では少なすぎます。「しっかりとヒアリングをさせていただきたいので、1.5時間、MAX2時間はいただけませんか?」とお願いしてみましょう。
この「MAX●時間までは確保してほしいです」という言い方がオススメです。顧客は時間切れになり良いシステム提案にならないことが嫌なので、多めに時間を取ってくれます。そして、おおよそ3回までのヒアリングを繰り返し、提案書と見積書を提出していくスタイルが多いと思います。時間を守りながら、少しでも多くのヒアリング時間をもらえる方法です。
ヒアリングの進め方 受注後
「受注後」はすでに顧客が提案側に正式発注をしています。課題解決のためにプロジェクトを進めていきますので、優先的に時間を取ってくれます。IT業界では要件定義と呼ばれる、最初にシステムの要件を明確にして、要件定義書にまとめるまでのフェーズが代表的な例です。
時間は3時間から4時間、ほぼ半日の時間を取ってくれるケースが多く、このような半日の要件定義を5回から10回程度行います。顧客側からも既存システムの設計書や社内資料が数多く提出され、資料を読み込んで疑問点をヒアリングしていきます。
顧客を理解しニーズを把握するために聴いてみる=ヒアリングの本質を達成するためには、顧客も提案側も時間をかけるというスタイルが大切です。そして、要件定義は計画力とまとめる力が重要ですので、ヒアリングしていく範囲を明確にして要件定義書に総括していきます。それで実際にヒアリングのテクニックを知っていきましょう。
ヒアリングのテクニックを知っておこう!
ヒアリングを上手く進めていくためのテクニックは、誰でも身につけたいスキルと言えます。最近ではリモート商談やオンライン打ち合わせが増えてきていますので、オフラインとオンライン別にヒアリングのテクニックを変えていかなければなりません。
また、本記事の営業とエンジニアが顧客にヒアリングをするケースでは、管理部門だけでなく、設計・開発の技術部門等の様々なタイプのビジネスパーソンが登場してきます。従って、聴きやすくする・顧客は話したくなるための心理的アプローチや非言語コミュニケーションも重要になってきます。
代表的なヒアリングテクニックをオフライン・オンライン・心理的アプローチ/非言語コミュニケーションに分けてご紹介していきます。
オフラインのヒアリング手法
最初に雑談をする
打ち合わせの前には必ず雑談をしましょう。笑いがあり笑顔が増えるような話がオススメです。なぜなら、「笑いや笑顔」はヒアリングをする前に、顧客を話しやすくさせる効果があるからです。人は誰でも笑っていたい生き物であり、笑うとリラックスして顧客ニーズに関する話がどんどん出てきます。鉄板の雑談は「ご近所話」が良いでしょう。詳しい内容は下記記事をご覧ください。
ヒアリングのフレームワークを使う
顧客のニーズを聴き出すためにはMEDDPICCのようなヒアリングフレームワークを使うと良いでしょう。大型案件に向いている手法で、利用する営業チームが増えています。詳しい内容は下記記事をご覧ください。
記事 MEDDPICC(メディピック)とは?外資系営業のフレームワークとして広がる理由
ヒアリング質問項目やヒアリングシートを作成・活用する
「製品・サービスを提案するため」と「案件を進捗させるため」には、ヒアリングのための質問項目を整理したヒアリングシートを作成し、活用すると良いでしょう。誰でも同じ品質で聴けるようになり、聴きモレがなくなります。詳しい内容は下記記事をご覧ください。
記事 営業の初訪問のヒアリング項目はこれだ!質問方法やヒアリングシートの作り方・テンプレートをご紹介
オープン型質問とクローズ型質問 ヒアリングではオープン型を多く使おう
ヒアリングの種類にはオープン型の質問とクローズ型の質問があります。簡単に説明すると、広げていきながら聴くやり方がオープン型質問、限定的に聴きだすやり方がクローズ型質問です。ヒアリングではオープン型質問を多く使った方が良いでしょう。なぜなら、顧客が「ニーズ=欲求」を話しやすくなるからです。現在の課題、要求したいこと、必要性の有無を深掘りしながら明確にヒアリングできます。詳しくは本記事のさいごのサービス内容やダウンロード資料をご覧ください。
オンラインのヒアリング手法
通常の2倍うなずく・ジェスチャーを大きく
オンライン打ち合わせでは顧客が話しやすくさせる環境づくりが大切です。通常よりも身振り手振りのジェスチャーを大きくするだけでなく、ヒアリングに入る前の顧客の話に対し、いつもの2倍以上うなずいてあげましょう。共感している表現力を増やすことが大切です。
心理的アプローチ/非言語コミュニケーションのヒアリング手法
座る位置はナナメに座る
初めて会う顧客は打ち合わせ中に営業やエンジニアに慣れて、リラックスするまで30分ぐらいかかると言われています。その理由は相手を警戒していたり緊張していたりするからです。このような心理的な問題をなるべく早く取り除くことが大切です。
そのためにまずできることは、顧客と少し離れて座り、打ち合わせをしましょう。一般的に顧客との距離が110センチ以上になると、目線をそらしにくくなり、早く打ち解けられると言われています。誰でも簡単にできる心理的アプローチであり、非言語コミュニケーションのヒアリング方法ですので、ぜひ実践してみてください。
このようなヒアリングテクニックを使い、上手に顧客のニーズを聴いていきましょう。
ヒアリング力を高めるための方法 ヒアリング研修
ヒアリング力を高めるための基本的な考え方や方法をご紹介してきました。しかし、様々な記事を参考にしたり、社内メンバーだけで取り組んだりすることだけでは限界があります。その限界をカバーしてくれるのは外部のヒアリング研修を受講するのが近道です。ヒアリングのプロから、営業とエンジニアがヒアリングスキルを高める方法を学ぶ選択肢も検討してみたらいかがでしょう?
質問1 ヒアリング研修は傾聴力やヒアリング力の向上に役立ちますか?
答え 傾聴とは顧客ニーズを徹底的に聴くことであり、要件定義等の長期間に渡るヒアリングに効果的です。このような力を身につけることは、社内の活動だけでは難しいでしょう。専門のプロから学ぶのが効果的でしょう。詳しい内容は下記記事をご覧ください。
記事 営業傾聴力と営業ヒアリングはどう違うの?課題整理をするための使い方
質問2 ヒアリング研修を提供してくれる会社はありますか?
答え ラシックマーケティング株式会社では「聴ける営業になろう!」という営業やエンジニア向けのヒアリング研修を提供しています。オープン型質問とクローズ型質問の使い方も研修の中で詳しくご紹介しています。そして、図1のように研修内容に対し高い評価をもらっており、面白い内容です。詳しくはダウンロード資料で「聴ける営業になろう!」のアジェンダやカリキュラムをご確認ください。
-1024x576.png)
まとめ
「ヒアリング力を高めよう!営業とエンジニアに必要なスキルを紹介」と題して、ご紹介してまいりました。ヒアリングと営業ヒアリングの違いや、顧客を理解しニーズを把握するための方法を解説しました。
ヒアリングのテクニックを少しだけご紹介しましたが、「聴く力」は数多くの種類や実践方法があります。そして、専門性の高い手法や考え方も求められます。まずは、上司や先輩が社内プロジェクトの中で勉強会やロープレ、OJT(同行指導)を実践してみましょう。社内で取り組んで、それでもヒアリング力が向上しないケースに外部の有識者に相談してみるのが良いと感じます。
顧客ニーズにも欲求があるように、営業とエンジニアも欲求を持つべきだと思います。営業なら受注したいという欲求、エンジニアならプロジェクトを成功させたいという欲求です。このようなヒアリングをする側にも欲求があることが、ヒアリングをうまく進めていける本質であり、ヒアリングの本質ではないでしょうか? 顧客ニーズ=欲求をヒアリングするために、営業やエンジニアも欲求を持って、顧客に接してみてください。
- ヒアリング力を高めよう!営業とエンジニアに必要なスキルを紹介
- 営業研修でスキルアップしよう!言語化されたノウハウを学ぶ
- 競合他社に勝つ3つの施策 調査・分析・資料・プレゼンで差をつけよう
- ビジネスで訊く、聞く、聴く 営業は実践できていますか?
- 報連相ができない人と上手い人の違い 営業提案力と比例する
- 意思決定者(DMU)に向かっていかない営業、動く営業の違い
- セールスと営業の違い 英語と日本語の良さをビジネスに活かそう
- 営業マインド 方法論だけでなく精神論も欲しがる若者の気持ち
- 課題解決型営業こそソリューション営業 提案方法を例で5つご紹介
- 営業の事前準備をよくわからないまま活動してきたあなたに 大切な3つの理由を紹介
- 雑談力を営業が高めるために 入り方やネタを例でご紹介
- 自動車営業のサシミとは?進捗と活動を一緒しない管理方法
- 標準化、平準化、手順化の違いとは?マーケや営業業務に求められること
- 営業企画と営業推進の仕事は面白くて、効果は絶大!部門を作ろう
- 営業予算の組み方や立て方とは?作り方までやってみよう!
- 顧客志向とは?顧客志向経営からマーケティングと営業を実践しよう
- 営業インセンティブと評価方法 有名企業の事例もコッソリご紹介
- IT営業やシステム営業はいらない?きつい?難しい?将来性?にお答えします
- 営業トークのコツ 3つのポイント つかみ・雑談ネタの基本セット
- 営業トーク・営業話法 課題と言わず、問題と言う意味とは?